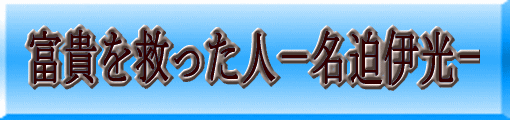
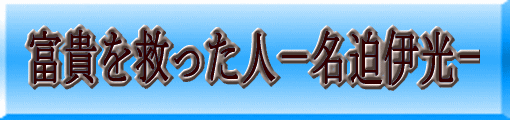
1 名迫伊光
名迫伊光(なさここれみつ)は,1676年,現在の高野町東富貴に生まれた。名迫家は,奈良時代の終わり頃(約1300年前),富貴・筒香を開たくした犬丸寅友(いぬまるとらとも)の子孫といわれている。その後,名迫家は,鎌倉時代の終わり(約700年前),富貴・筒香の両荘園(りょうしょうえん)の管理者に任命されたといわれる。江戸時代には高野山の寺院の領地になっていた蕗村(ふきむら)の大庄屋をつとめていた。伊光は幼い頃の名前を亀之丞(かめのじょう)といい,大きくなるにつれ,人の言うことを聞かない乱暴者になっていた。父の伝右衛門(でんえもん)が,「わたしには10人の子があったが,みな若死にしてしまい,この乱暴者だけが一人残った。名迫の家もこれで終わりだ。」となげいたほどであった。1698年,父の伝右衛門は58才で亡くなった。
この父の突然の死が,伊光の性格や生活を一変させた。伝右衛門の心配とは反対に,朝早くから夜遅くまで農業に励み,重い荷物を背負い険しい道も苦にせず大阪や和歌山方面まで行商に出かけた。一年中ほとんど休むことなく,身を粉にして働く姿に人々は目を見張った。富貴は,土地がやせており,高冷地で夏気温が上がらない気象条件も重なり,人々の生活は決して楽なものではなかった。そのため,伊光は,生活に困っている人がいると夜中にこっそりとお金や生活に必用な物を届けた。年貢を納められない家があれば,すすんで米やお金を貸した。そして,米やお金を返してほしいとさいそくすることはなかった。もし返せない人がいても「みんなの役に立ててよかった」と喜ぶように人になっていた。伊光は,神仏をうやまう心が厚く,父の伝右衛門が亡くなって13年目,村の宝ぞう院や観音堂を再建したり,高野山奥の院の18町の道路をしゅうぜん・掃除をさせたりした。そのような伊光を「富貴の生き神」として祭るようになったきっかけは,享保3年(約300年前)の大飢饉(食べ物がなくなるこ)であった。
 |
 |
2 享保の大飢饉
歴史上で有名な享保の大飢饉とは,享保17年(1732年)西日本をおそったイナゴの害による不作をいうが,富貴では享保3年(1718年)をピークとする不作のほうが被害が大きかった。それまでの4年間雨不足で不作続きであった上に「100年以来の大干ばつ」が加わり大きな被害を出した。蕗村では,135石(こく)1斗(と)(約2500㍑)の田がかれ、人々はワラを煮て食べたりフキ・ワラビ・ヨモギの根を掘ったりして飢えをしのごうとしたが,100戸足らずの村で101人が餓死し,31軒が空き家となった。隣の村を含めると,168人が餓死し,55軒が空き家となった。若くて働ける者は村を捨て,病人や老人や小さな子どもだけが残った。
これらの様子を見かねた伊光は,倉を開いて村人に米を与えた。また,自分が和歌山城下に持っていた貸家や家のいろいろな道具までも売り払って村人を助けた。村を去った若者を,自ら徒歩で10里(約40キロメートル)を行って呼び戻し,農具と種もみの代金を与え元の村に帰らせた。
さらに,当時山深い山村であったので,猪・鹿・猿が真っ昼間でも村道を列を組んで歩くほど数多く山から下りてきた。田畑の穀物は実らないうちに掘り返し食い散らしほとんど収穫できない年が多かった。しかし,寺院の領地であるため退治することができず涙をのんで荒らすにまかせるより仕方がなかった。伊光はこれを嘆き,数回高野山へ登り,これらを退治してもかまわないようにしてほしいと願い出た。そして,鉄砲の名人を銀30貫(約30万円)雇い,8年間で1170頭の猪・鹿・猿を退治した。また,毎年,この名人に与え,耕作時ごとに猪・鹿・猿などの退治をしてもらった。
 |
 |
 |
 |
3 高野山への嘆願
伊光は,高野山へ登り,村の悲しい状態を訴え,まだ納めていない年貢銀31貫目を納めなくてもいいようにしてほしいこと,村に残った農民が,これからも安心して暮らせるように年貢を少なくしてほしいことを願い出た。高野山へ1000回も足を運んだという話が残っている。9月村の悲しい様子を見た高野山は,伊光の願いを取り上げ,翌年2月正式に確認した。それによると,「まだ納めていない年貢は収めなくてもいいようにする」「特に被害の大きかった19石余りの土地は米が作れない田として田畑の地図からけすことにする」「享保3年から10年間、田畑の年貢を少なくし,茶畑の年貢をもらわないことにする」というものだった。伊光の村を思う気持ちとふだんから自腹を切っても年貢を完全に納めてきた心が報われ,村は救われたのである。



4 「蕗」から「富貴」へ
1724年11月24日,村人は一つの社を建てて,名迫権現と名付けて伊光を祭った。その恩を子孫に伝え,村の繁栄を願うためであった。これは伊光48才のことであり生きながらにして神になったのである。伊光の努力でよみがえった村は,これまでの「蕗」の地名を「富貴」と改め,その復興を喜びあった。
富貴には,「やれおせ」という盆踊りがある。これは,享保の大飢饉を乗り越えた村人が,飢饉で亡くなった人々の死後の幸福を祈り,富貴を再び栄えさせようという願いを込めて始めたものである。富貴小・中学校の運動会では毎年「やれおせ」を踊っている。
伊光の孫である伴次郎行雄(ばんじろうゆきお)も名庄屋として人望が厚く,1782年の飢饉では,村の救済に全力を尽くしたので,村人は伊光の話にならって,1786年再び社を建立した。現在,東富貴にある名迫明神社には,伊光とともに行雄も祭られている。